「任意後見人」と調べたら「後悔」って出て「本当!?なんで!?」と疑問に思ったので調査した結果を共有します。
結論、「任意後見人」には意外と知られてない良いところがあるので全員が後悔するとは限りません。
「任意後見人」の経験者に聞いたリアルな口コミを続きでご紹介します。この記事を最後まで読めば「任意後見人」で後悔することはなくせます。必ず最後まで見てね!
 筆者
筆者この記事を読むと、任意後見人選びで後悔しないための具体的なアドバイスが分かります。
- 任意後見人を選ぶ際に後悔しないための対策が理解できる
- 任意後見人が必要ないケースとその理由が分かる
- 任意後見人を選ぶ際の注意点やアドバイスが分かる
- 費用や報酬など、任意後見人に関する費用面の理解が深まる
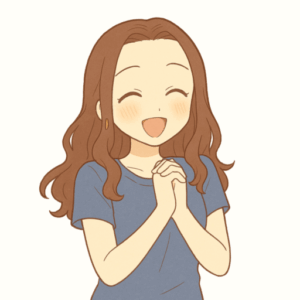
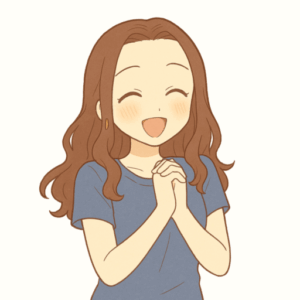
こんにちは!この記事を書いた「もえ」です。
「後悔先に立たず」という言葉がありますが、この記事を読んだ人の後悔がなくなるように頑張って執筆しています。
ぜひいろんな記事を読んでいってください。
特定の商品やサービスの名誉を毀損するつもりは一切ありません。修正依頼がございましたらお手数ですが、お問い合わせページよりお願いします。すぐに対応いたします。なお記事執筆にあたっては、消費者庁や国民生活センター・厚生労働省など、信頼性の高い情報を参考にしつつ、公式HPの最新情報を取り入れています。
任意後見人で後悔!?デメリット解決策とよかった派の口コミ7選
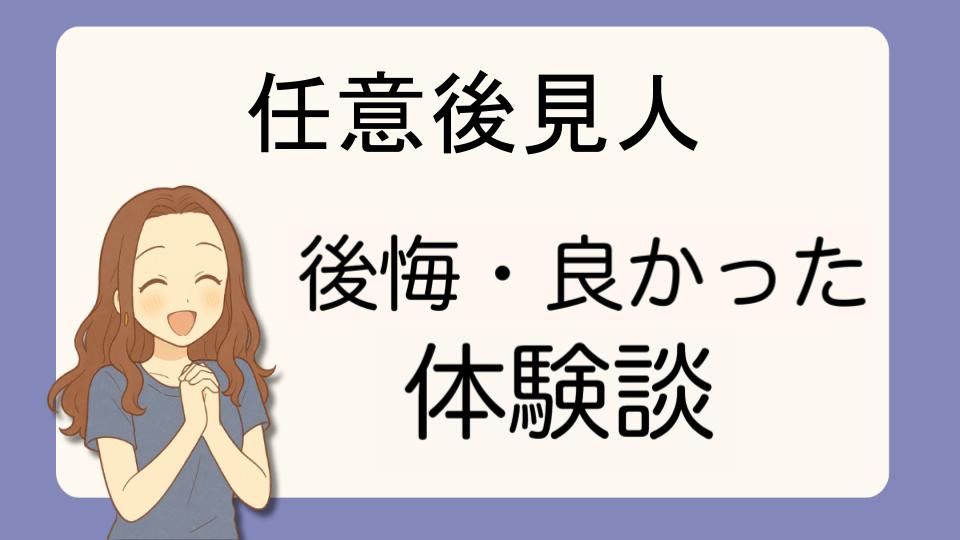
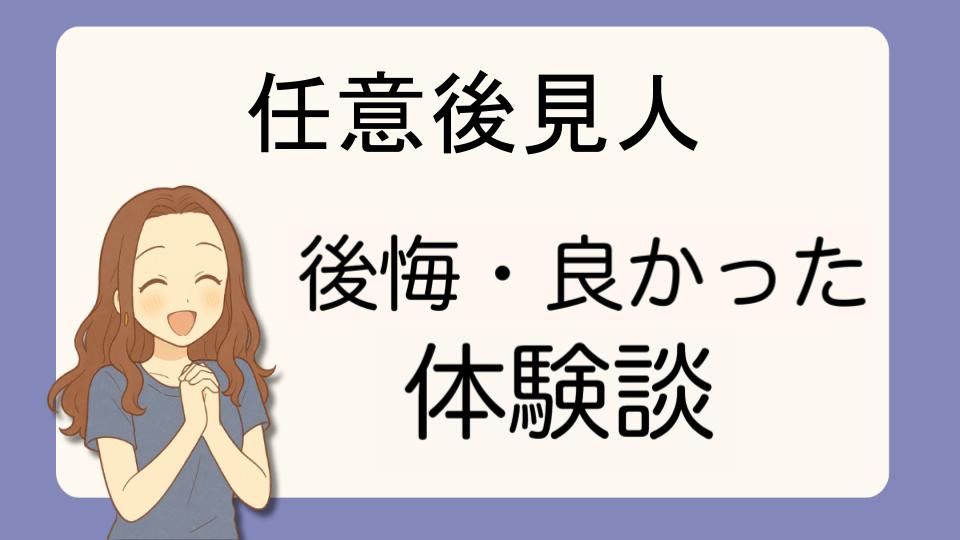



任意後見人で後悔した人から聞いたデメリット、後悔しなかった人から聞いた良かったことをご紹介します。
後悔した人の口コミ・デメリット



任意後見人で後悔した人のエピソードをご紹介します。



信頼できない
任意後見契約を結んだ後、後見人が信頼できる人でないことに気付きました。事務的で冷たい対応に心が折れ、家族が手を貸すべきだったと思っています。契約内容をもっと慎重に考えるべきでした。(男性)



費用が高すぎる
任意後見人の費用が思った以上に高く、家計に負担がかかりました。最初にもっと費用について説明を受けていれば、違う方法を選んだかもしれません。(女性)



対応が悪すぎる
自分の信頼できる人を後見人に選びましたが、思った以上に対応が不十分でした。もっと専門家に依頼すれば良かったと後悔しています。(男性)



自分の意思が反映されない
後見人が私の母の財産を管理してくれましたが、重要な決定を一方的に下されることが多く、母の意志が反映されていないと感じました。(女性)



手続きの遅れに後悔
任意後見契約を結んだ後、後見人選任に時間がかかり、いざという時にサポートが遅れました。もっと早く手続きを進めておくべきでした。(男性)



効果を実感できなかった
後見人が制度を利用しても十分にサポートしてくれず、後悔の気持ちが強くなりました。もっと効果的な支援を得る方法があったはずです。(女性)



意思疎通ができない。信頼できない。
契約した後見人が必要な時に対応してくれなかったり、意思疎通がうまくいかなかったりして、信頼感が薄れ、後悔しています。(男性)
良かったと思った人の口コミ・メリット



任意後見人の経験者から聞いたメリットをご紹介します。



任意後見制度で安心
認知症の兆候が見られたとき、事前に任意後見制度を利用して信頼できる後見人を選んでおいて本当に良かったです。後見人が私の財産管理や生活支援をしっかりと行ってくれ、家族に負担をかけることなく、安心して生活できるようになりました。(男性)



支援が心強かった
任意後見制度を利用し、専門知識を持つ後見人に財産管理や生活支援をお願いしました。おかげで認知症が進行しても、困ることなく必要な手続きやサポートを受けられ、安心して暮らすことができました。(女性)



信頼できる後見人に助けられた
私の母は任意後見制度を利用して、後見人に自分の意思をしっかりと反映させていただきました。認知症が進行し判断力が低下したときも、後見人のおかげでスムーズに日常生活を送ることができ、助かっています。(男性)



家族の負担を減らせた
家族に迷惑をかけたくないという思いから任意後見制度を利用しました。後見人が生活面の支援を行ってくれ、家族が不安を感じることなく過ごすことができました。依頼して本当に良かったです。(女性)



生活の質が守られた
任意後見制度を利用して、後見人に財産管理や生活支援をお願いしました。後見人は私の希望をしっかりと尊重し、必要な支援を提供してくれたため、安心して日々を過ごしています。(男性)



後見人のおかげで生活が安定した
認知症が進行し、生活に不安を感じていたとき、任意後見制度により後見人に管理をお願いしました。おかげで、財産の管理や医療支援も円滑に行われ、生活が安定して過ごせるようになりました。(女性)



後見人のサポートで不安解消できた
任意後見制度を利用し、後見人に自分の財産や生活支援をお願いしました。後見人がしっかりと私の意思を尊重してサポートしてくれたおかげで、日々の生活に安心感を持つことができました。(男性)
任意後見人で後悔しないためのコツ
任意後見人の経験者から聞いた後悔しないためのコツをご紹介します。迷ってる人は参考にしてみてください。



信頼できる後見人選びが最も重要
任意後見人を選ぶ際には、親しい家族や信頼できる専門家を選ぶことが最も大切です。後見人は、本人の生活や財産を管理する責任があるため、信頼関係が築ける人を選ぶことで後悔を避けることができます。また、選定後も定期的に関わりを持つことが重要です。(男性)



事前に契約内容を明確にする
契約を結ぶ前に、後見人の役割や範囲を事前に明確に決めておくことが大切です。例えば、財産管理や生活支援に関する具体的な内容をきちんと決めることで、後から不満や誤解が生じることを防げます。文書化しておくことがポイントです。(女性)



後見監督人の役割を理解する
後見監督人を選任することで、後見人の管理や行動が適切かどうか第三者が監視することができます。任意後見制度には監督人が必要な場合もあるので、誰に任せるか慎重に決め、定期的にその活動を確認することが後悔を避ける秘訣です。(男性)



費用について事前に確認する
任意後見契約には初期費用と後見人報酬がかかります。事前にその費用をきちんと把握し、無理のない範囲で計画を立てることが大切です。特に後見人に支払う報酬は契約でしっかり決め、予算内で運用するようにしましょう。(女性)



後見人の選任を再評価すること
任意後見制度を利用しても、状況が変わることがあります。定期的に後見人を再評価し、契約内容や後見人の適性を見直すことが大切です。状況に応じて適切な修正を加えることで、後悔することなく円滑に管理を進めることができます。(男性)



予測できるリスクに備える
予測できるリスクに対処するため、後見人ができないことを事前にリスト化しておくと良いです。契約に記載されていない項目は後見人に行わせることができません。しっかりと範囲を決め、必要なら補足契約を追加することが重要です。(女性)



後見人と定期的に連絡を取る
後見人と定期的に連絡を取ることで、状況がどうなっているのか、管理が適切に行われているのかを確認することが大切です。必要であれば定期的な報告を義務付け、透明性を保つことで安心して任意後見制度を活用できます。(男性)
任意後見人で後悔!?よくある質問
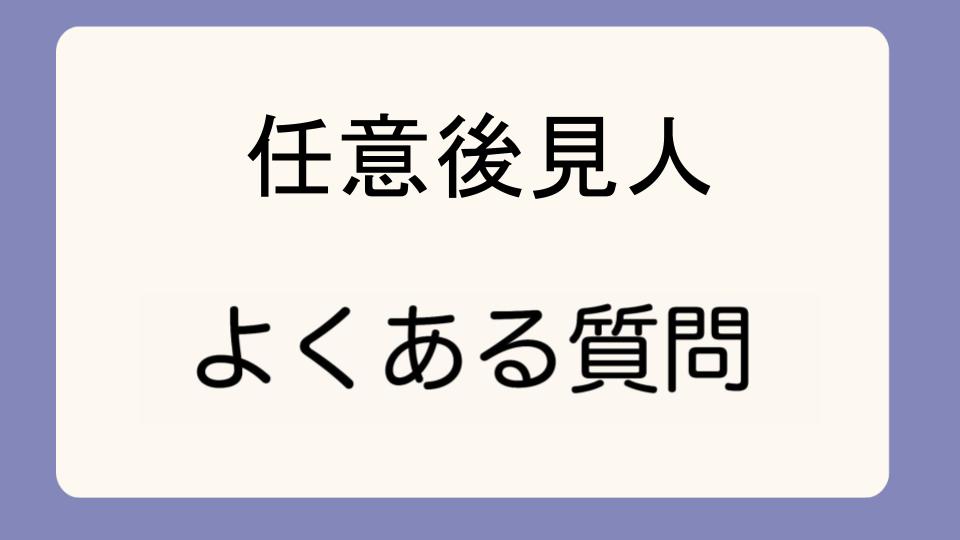
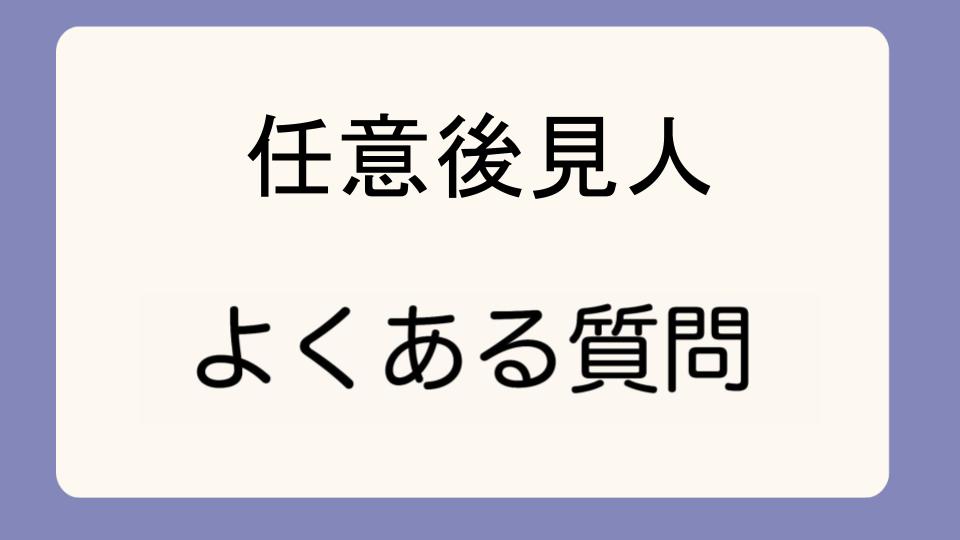
任意後見人で後悔に関連してよくある質問をご紹介します。
任意後見人になるにはどうすれば良いか
任意後見人になるためには、まず任意後見契約を結ぶ必要があります。契約時には、後見人となる人を指定し、その人が将来、判断能力が低下した際に本人を支援する役割を担います。契約は公正証書で作成し、法務局で登記する必要があります。
契約の内容としては、本人の財産管理や生活支援、医療契約などが含まれることが一般的です。この契約が有効になるのは、本人が判断能力を失った時点です。そのため、契約を結ぶ際は十分に計画を立ててから実行することが大切です。
任意後見人になるには、本人の意思を反映させることが重要です。そのため、後見人としての責任や役割をしっかりと理解し、事前に話し合いを行うことが不可欠です。また、後見人の選任には法律的な要件があるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
契約を結ぶ際に気をつけなければならない点は、後見人がその権限を超えて判断することがないように、契約書で具体的な内容を定めておくことです。これにより、後々のトラブルを防ぐことができます。
また、後見人の選定においては、信頼できる人物を選ぶことが大切です。家族や友人など、後見人が本人の意思を尊重できる人物であることが必要です。信頼関係が築ける相手を選ぶことが後悔を防ぎます。
任意後見制度は、個々の事情に合わせて柔軟に対応できるため、早期に契約を結んでおくことが望ましいです。判断能力が低下してからでは契約が無効になってしまう可能性があるため、元気なうちに準備を進めることが大切です。



後見人選びは信頼が第一です。事前にしっかりとした話し合いをすることが、後悔しない鍵となります。
任意後見制度を利用した後悔とは
任意後見制度を利用したものの、後悔したという声もあります。特に、後見人として選んだ人が期待通りに機能しなかった場合、制度がうまく機能しないことがあります。後見人が誠実に管理できなければ、本人の財産が守られないことにもつながりかねません。
また、契約時に明確に決めた内容を後見人が意図的に無視してしまう場合もあります。例えば、特定の財産を守るために後見人を指定したにも関わらず、その財産が誤って売却されてしまったというトラブルが報告されています。
さらに、後見人が選任されても、実際に業務が開始されるまでに時間がかかるため、急な支援が必要な状況で役に立たないこともあります。特に、判断能力が急速に低下する場合に、後見人が適切に対応できない可能性があります。
このような後悔を避けるためには、契約内容を十分に確認し、後見人の選任にも慎重を期す必要があります。また、後見人が業務を始めるタイミングや内容について、予め打ち合わせをしておくと良いでしょう。
後見人に選ばれる人は、信頼性だけでなく、能力や経験も重要です。後見人には家族や親しい友人を選ぶこともできますが、専門家を選任する場合もあります。専門家を選ぶことで、確実なサポートを受けることができます。
任意後見制度を利用する際には、信頼できる後見人を選ぶことが最も重要です。後見人が安心してサポートできる環境を整えることで、後悔を防ぐことができます。



後見人の選任が重要。事前にしっかりと打ち合わせをしておくことでトラブルを避けられます。
任意後見人は本当に必要かを考える
任意後見人が本当に必要かどうかを考える際、まず重要なのは、自分の健康状態や将来のリスクに対する認識です。もし、自分が将来、判断能力を失った場合に備えたいのであれば、任意後見人を指定することで安心できます。
任意後見人が必要だと感じる場合の一つは、特に財産が多く、管理が複雑な場合です。事業を営んでいる人や不動産を多く所有している人は、任意後見人を選ぶことで、自分が判断能力を失った時に、財産管理を確実に行えるため、リスクを減らすことができます。
逆に、単純な資産管理や日常的な支援であれば、任意後見人を選任する必要はない場合もあります。例えば、生活が安定しており、誰かに頼む必要がないと感じている人にとっては、後見制度を使うことが過剰な対策となることもあります。
また、後見人を選ぶことによって、自分の意思に反する行動をとられることを懸念する場合もあります。そのため、自分がしっかりと意思表示をしておけるうちに、必要な範囲で後見人を選ぶようにすることが大切です。
もし、後見人を選ぶことで不安や負担が増えると感じる場合は、他の選択肢を検討することも重要です。例えば、家族信託などの方法で財産管理を行うこともできます。
任意後見人を選ぶ前に、必要性をしっかりと見極め、将来の不安に備えることが大切です。自分にとって最適な方法を選ぶことで、安心して生活を送ることができるでしょう。



必要性をよく考え、慎重に判断することが大切です。自分にとって最適な選択をしましょう。
任意後見人ができることとできないこと
任意後見人は、主に財産管理や生活支援、医療契約の取り決めを行います。契約内容に基づいて、本人の生活全般をサポートすることができます。 例えば、本人が判断能力を失った後は、銀行口座の管理や財産の売却を行うことができます。
しかし、任意後見人には制限があります。契約に記載された範囲を超えて活動することはできません。 例えば、後見人が契約に記載のない内容で新たな契約を結ぶことはできません。事前に決めた範囲内でしか行動できないため、後見人の権限は明確に定める必要があります。
また、後見人は本人の意向を尊重しながら行動しなければなりません。任意後見人は、本人が意思表示できる間に設定された契約に基づいて支援を行うことが求められます。 つまり、後見人が行動するためには本人の意思確認が最優先されます。
そのため、後見人が不正に財産を管理したり、本人に不利益な判断をした場合、その行動には法的責任が伴います。
後見人ができる範囲をしっかりと明確にしておくことで、後悔しない制度の活用ができます。
しかし、後見人ができないこともあります。例えば、本人の死亡後の財産管理は任意後見人の責任外です。後見人はあくまでも生前の支援にとどまり、死亡後の手続きには関与できません。 その点は家族信託や遺言など、別の制度を考慮する必要があります。



後見人の範囲を明確に決め、契約内容をしっかり確認することが重要です。
任意後見制度の利用者が少ない理由
任意後見制度の利用者が少ない主な理由は、この制度の利用が複雑であると感じる人が多いからです。 例えば、契約を結ぶには公正証書を作成し、法務局に登記する必要がありますが、この手続きに対する敷居が高いと感じる人も少なくありません。
また、任意後見制度は自分が判断能力を失う前に契約を結ぶことが前提です。そのため、将来に不安を感じても、今すぐにその準備をする必要性を感じない人も多いです。 実際に制度を利用するのは、認知症や判断能力低下が現実味を帯びてからであるため、事前に契約を結んでおく人は限られています。
さらに、任意後見人を選定する際、誰に後見人を任せるかという問題もあります。信頼できる後見人を選ぶことができず、制度を利用しない人もいます。 特に後見人には大きな責任が伴うため、家族や親しい友人に頼むのが難しいと感じる場合があるのです。
制度に対する認知度が低いことも利用者が少ない理由の一つです。多くの人は、この制度の存在自体を知らないか、利用しなくても大丈夫だと考えています。
また、費用面でも不安があります。任意後見契約の費用や、後見監督人への報酬が発生するため、費用の面でも敷居が高く感じられることがあります。
そのため、専門家のサポートを受けるためには、いくらくらい費用がかかるのか、またその後の手続きにどれほどの手間がかかるかを不安に思う人が多いのです。



任意後見制度は費用や手続きが複雑で、敷居が高いと感じる人が多いのが現実です。
任意後見人に求められる費用とは
任意後見人の費用には、まず契約時に必要な費用があります。任意後見契約は公正証書で作成し、そのための公証人手数料が発生します。契約書の作成や登記手続きにかかる費用を事前に把握しておく必要があります。
また、任意後見人には、業務報酬が支払われることがあります。 任意後見人の報酬は、契約書に記載された内容に基づいて決定されます。例えば、財産管理にかかる費用や、日常的な支援にかかる報酬です。
後見人の報酬は、後見人が家族や友人の場合、無償で引き受けてもらうことができますが、専門家の場合は一定の報酬が発生します。報酬の相場は、財産の管理額や業務の内容によって異なります。
さらに、任意後見制度には、任意後見監督人への報酬が必要です。 任意後見監督人は、後見人の活動を監督する役割を担います。監督人への報酬は家庭裁判所が決めますが、その額は管理対象の財産額に応じて変動します。
費用が発生することで、任意後見制度の利用をためらう人もいますが、長期的に見て、適切な管理を行ってもらうための費用であると考えることが重要です。
任意後見人にかかる費用は、初期費用から報酬、監督人の費用まで多岐にわたります。予算をしっかり立て、どの範囲で後見をお願いするのかを明確にしておくことが大切です。
そのため、利用前にしっかりと費用の見積もりを取ることが、後悔しないための大切なステップです。



任意後見人には多くの費用がかかるため、事前にしっかりと見積もりを取ることが必要です。
任意後見人が必要でないケースとは
任意後見人が必要でないケースには、すでに判断能力が低下している場合があります。任意後見制度は、本人がまだ判断能力を持っているときに契約を結ぶ制度です。したがって、すでに判断能力を失った場合は、法定後見制度を利用するのが適切です。
また、財産が少なく、日常的な支援が不要な場合も任意後見人を選任する必要はありません。年金だけで生活している場合や、特別な支援が必要ない場合には、この制度を利用しなくても困ることは少ないでしょう。
任意後見人は、財産管理や生活支援をお願いするために利用されることが多いですが、こうした支援が必要ない場合は、別の方法で対応することが可能です。例えば、定期的な健康診断や見守り契約などで十分です。
さらに、信頼できる後見人がいない場合は、無理に任意後見人を選任するのは避けるべきです。後見人選びが難しい場合、他の方法(例えば、成年後見制度)を検討した方がいいかもしれません。
また、任意後見人にかかる費用が高額になる場合も、この制度を利用する必要がないケースがあります。費用を抑えるためには、他の方法を模索することが重要です。
場合によっては、家族間で十分に信頼できる体制を作り、後見人を設定せずとも問題なく生活できる場合もあります。



任意後見人が必要かどうかは、まず自分の状況に応じて判断することが大切です。
任意後見監督人の報酬について知っておくべきこと
任意後見監督人は、後見人の活動を監視し、適切な支援が行われているかを確認する役割を担います。監督人の報酬は、管理する財産の額に応じて決まります。 管理する財産が多ければ、それに比例して報酬も増えるのが一般的です。
報酬は家庭裁判所が定めることが多く、一般的には月額数千円から数万円程度となります。具体的な金額は、管理対象となる財産額や業務の内容により異なります。
また、任意後見監督人は必ずしも専門家である必要はありませんが、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれることが多いです。専門家による監督は、より確実な支援を受けるために重要な要素となります。
一方で、監督人を選任すること自体が負担になる場合もあります。監督人を選ぶには、申請が必要であり、手間がかかるため、利用者が減少する原因の一つになっています。
また、報酬が必要なことから、後見人が無償で活動する場合、監督人にも報酬が必要になる点に注意が必要です。
そのため、監督人の選任を検討する際は、費用面での負担をしっかりと確認し、どのような専門家に依頼するかを決めることが大切です。



任意後見監督人の報酬は、後見の状況によって異なるので、事前に確認しておくことが重要です。
弁護士が任意後見人になるメリットとデメリット
弁護士が任意後見人になる最大のメリットは、法律的な知識と経験を活かして、適切な支援を行えることです。 財産管理や契約書作成の際、法的に問題がないかをチェックするため、安心して任せることができます。
弁護士は法律に精通しており、特に複雑な財産管理や問題解決が求められる場合に有効です。信頼できる後見人として、法律的なトラブルを回避しやすいという点が大きな魅力です。
また、弁護士が後見人になると、後見の透明性や適法性が保たれやすいため、家庭内でのトラブルを未然に防ぐことができます。家族間での信頼関係に不安がある場合も、弁護士を後見人にすることで公正さが確保されます。
しかし、デメリットもあります。弁護士に後見人を依頼する場合、報酬が高額になることが多いです。弁護士は専門家であり、その分費用もかかるため、一般の後見人よりも費用負担が重くなります。
また、弁護士は通常、日常的な支援よりも法的な業務に集中するため、本人の日常生活を細かくサポートするという点では他の後見人に劣る場合があります。
そのため、弁護士を後見人にするかどうかは、どれほど法的なサポートが必要か、そして費用に見合った価値があるかをしっかりと考える必要があります。



弁護士が後見人になる場合、専門的な知識が活かせますが、費用が高くなる点を考慮しましょう。
まとめ|後悔しない任意後見人選び|失敗しないためのポイント
最後にこの記事のポイントをまとめてご紹介します。
- 任意後見人を選ぶ際の後悔を避ける方法を解説
- 任意後見人が不要なケースとその対策について触れる
- 弁護士が任意後見人になるメリットとデメリットを紹介
- 任意後見監督人の報酬に関する知識を提供
- 判断能力が低下している場合の後見制度の選び方を解説
- 任意後見人にかかる費用についてしっかり説明
- 任意後見人ができることとできないことを明確にする
- 任意後見人を選ぶ際に押さえておくべき注意点
- 信頼できる後見人がいない場合の対応方法を紹介
- 費用負担を抑える方法についての実践的なアドバイス
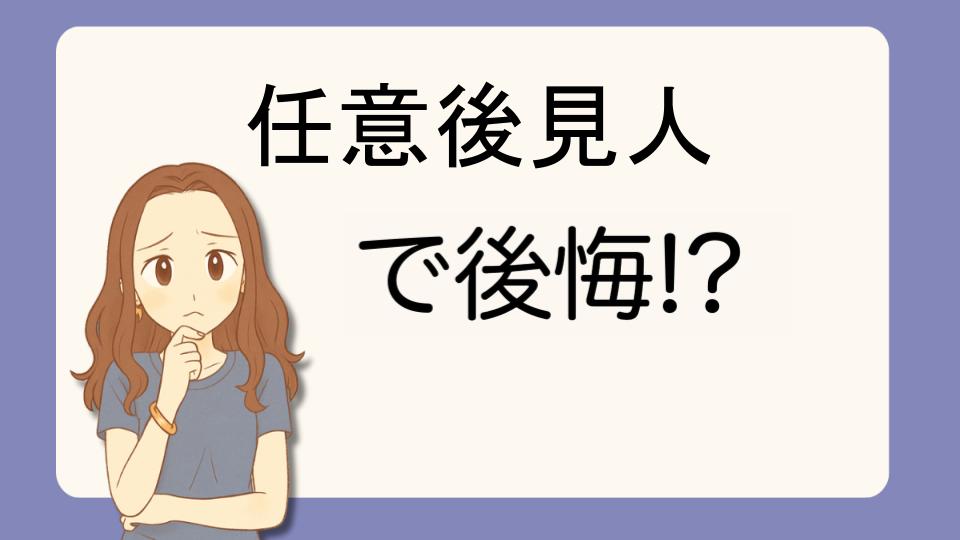
コメント