「ベビーサイン」と調べたら「後悔」って出て「本当!?なんで!?」と疑問に思ったので調査した結果を共有します。
結論、「ベビーサイン」には意外と知られてない良いところがあるので全員が後悔するとは限りません。
「ベビーサイン」の経験者に聞いたリアルな口コミを続きでご紹介します。この記事を最後まで読めば「ベビーサイン」で後悔することはなくせます。必ず最後まで見てね!
 筆者
筆者この記事を読むと、ベビーサインを試してみるべきか、どんな点に気を付ければ後悔しないかがわかります。
- ベビーサインで後悔しないために必要なポイントが理解できる
- ベビーサインを始める適切な時期について理解できる
- 赤ちゃんとのコミュニケーションを深める方法がわかる
- ベビーサインの注意点や失敗しないための対策がわかる
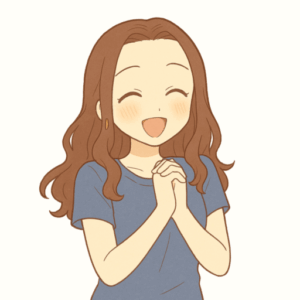
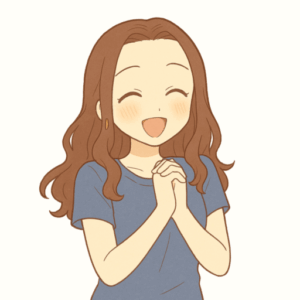
こんにちは!この記事を書いた「もえ」です。
「後悔先に立たず」という言葉がありますが、この記事を読んだ人の後悔がなくなるように頑張って執筆しています。
ぜひいろんな記事を読んでいってください。
特定の商品やサービスの名誉を毀損するつもりは一切ありません。修正依頼がございましたらお手数ですが、お問い合わせページよりお願いします。すぐに対応いたします。なお記事執筆にあたっては、消費者庁や国民生活センター・厚生労働省など、信頼性の高い情報を参考にしつつ、公式HPの最新情報を取り入れています。
ベビーサインで後悔!?デメリット解決策とよかった派の口コミ7選
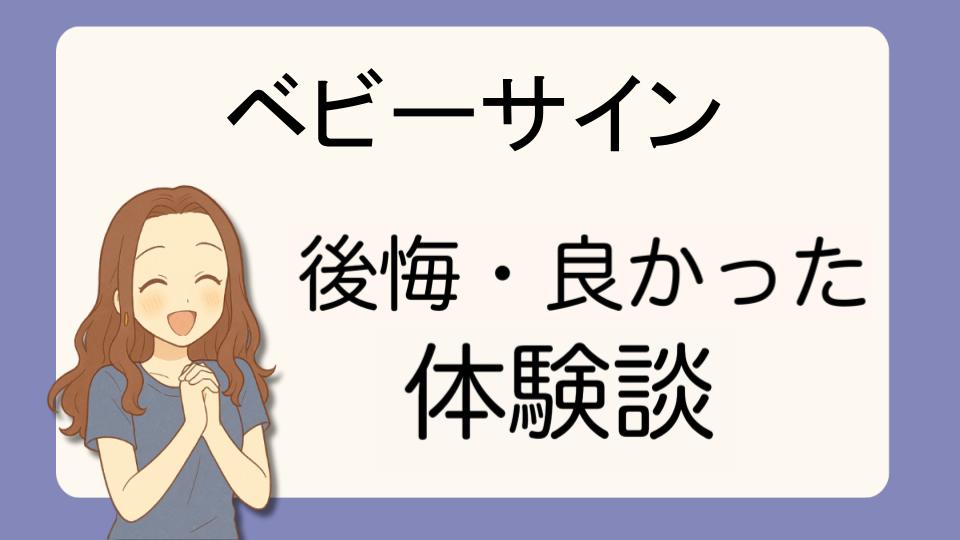
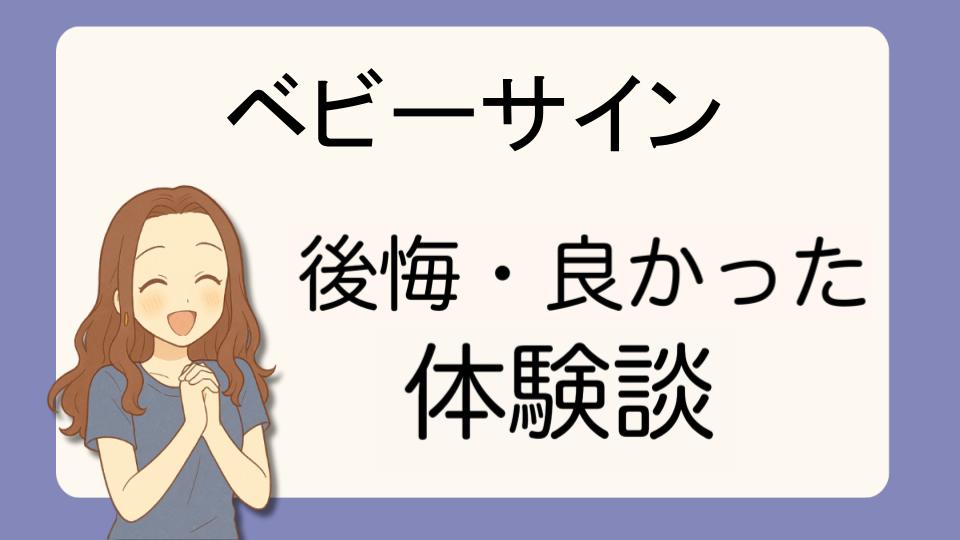



ベビーサイン」で後悔した人から聞いたデメリット、後悔しなかった人から聞いた良かったことをご紹介します。
後悔した人の口コミ・デメリット
ベビーサインで後悔した人のエピソードをご紹介します。



ベビーサインを試したけど、言葉の遅れが心配に
最初は上手くいきましたが、サインに頼りすぎて言葉の発達が遅くなった気がして後悔しています。毎回サインで通じてしまうので、早く言葉を覚えてほしいと思ってしまいました。(女性)



ベビーサインの教室に通わず後悔
自分で本を参考にして始めたものの、サインを覚えてくれない期間が長く、ベビーサイン教室に通えば良かったと思っています。焦りが強くなり、子どもに負担をかけてしまいました。(女性)



ベビーサインで混乱してしまった
サインを覚えさせる過程で、娘が次々とサインを覚える中で、息子は混乱してしまい、かえって反応が遅くなった気がして後悔。無理に教えすぎたかもしれません。(女性)



サインを多く覚えさせすぎて疲れた
ベビーサインは便利だと思って数多く覚えさせましたが、後で振り返るとサインが増えすぎて、どれも覚えきれない状態に。もっとシンプルにしておけば良かったです。(男性)



サインが通じたのに言葉の発達が遅れて不安
お腹が空いた時や飲み物を欲しがる時にサインを使うとすぐに通じましたが、言葉が出るのが遅くなり、焦ってしまいました。ベビーサインが裏目に出たような気がしています。(女性)



使い方がわからず途中でやめた
最初はベビーサインに興味を持って取り入れましたが、どのタイミングで使うべきか分からず、途中でやめてしまいました。結局、他の方法で伝えた方が簡単でした。(男性)



ベビーサインを始めたが反応がなかった
最初はやり方も気をつけて教えていましたが、息子が反応しなかったので、どんどん不安になり、無理にサインを教え続けてしまった。結果、成長に焦りを感じました。(女性)
良かったと思った人の口コミ・メリット



ベビーサインの経験者から聞いたメリットをご紹介します。



赤ちゃんとのコミュニケーションがスムーズになった
ベビーサインを始めてから、赤ちゃんが「おっぱい」や「もっと」といったサインを使って自分の欲求を伝えるようになり、コミュニケーションがスムーズになりました。これで何を求めているのか分かりやすく、育児が楽になりました。(女性)



育児のストレスが減り、育児が楽しめるようになった
赤ちゃんがサインを覚え、欲しいものを伝えてくれるようになったおかげで、イライラが減り、育児が楽しくなりました。「おしまい」や「もっと」といったサインを使ってくれるので、反応も早く、ストレスが減ったのが大きなメリットです。(女性)



サインで赤ちゃんの意思を理解でき、安心感が増した
赤ちゃんが「おいしい」や「飲む」などのサインを使うようになり、意思疎通ができるようになったことで、赤ちゃんが何を求めているかすぐに分かり、安心感が増しました。育児の不安が減り、心の余裕ができました。(男性)



言葉の発達を促進する助けになった
ベビーサインを始めたことで、赤ちゃんが「もっと」や「おしまい」などを使うようになり、言葉の発達がスムーズに進んだ気がします。サインで自分の意思を伝えた後、言葉で表現するようになったので、育児が充実しました。(女性)



赤ちゃんとの絆が深まり、育児が楽しくなった
ベビーサインを使うことで、赤ちゃんと心の通じ合いを感じ、育児がより楽しく、充実感を持てるようになりました。特に「痛い」や「おいしい」など、簡単なサインを使ってくれるようになり、赤ちゃんとの絆が深まりました。(女性)



赤ちゃんのニーズを理解しやすくなった
赤ちゃんがサインで自分のニーズを伝えてくれるようになり、何が欲しいのかすぐに分かるようになりました。「お腹空いた」「おしまい」など、普段の生活でサインを活用できるので、育児がスムーズに進みました。(男性)



赤ちゃんがサインを覚えたことで育児に自信が持てた
赤ちゃんがサインを覚えて、自分の意思をしっかり伝えられるようになったことで、育児に対する自信が持てました。言葉が出る前に意思疎通ができるので、日々の育児に安心感を持ちながら取り組めるようになりました。(女性)
ベビーサインで後悔しないためのコツ
ベビーサインの経験者から聞いた後悔しないためのコツをご紹介します。迷ってる人は参考にしてみてください。



赤ちゃんのペースに合わせて無理なく進める
最初はサインを覚えるのが遅くても焦らず、赤ちゃんのペースに合わせて進めました。無理に覚えさせず、楽しむ気持ちで進めることで、後悔なくサインを導入できました。(女性)



最初は簡単なサインから始める
赤ちゃんには最初に「おっぱい」「おしまい」などの簡単なサインから始めました。あまり多くのサインを覚えさせようとせず、少しずつ増やしていくことで、混乱せずに習得できました。(男性)



サインと一緒に声かけを忘れない
サインを使う際、必ず声かけも一緒に行うことを意識しました。これにより赤ちゃんはサインだけでなく、言葉にも興味を持ち、後悔しない形で言語発達を促進できました。(女性)



毎日サインを使って繰り返し教える
日常生活の中で、食事やお風呂のタイミングでサインを繰り返し使いました。赤ちゃんは繰り返しで覚えるので、毎日の生活の中で自然にサインを学べるようにしました。(男性)



サインと同時に他の方法でも意思疎通を図る
サインだけに頼らず、赤ちゃんとたくさん話しかけることで、サインと一緒に言葉も学べるようにしました。サインはあくまで補助的な役割として活用することが重要です。(女性)



赤ちゃんの反応を見て焦らず進める
サインを覚えるスピードに個人差があるので、赤ちゃんが反応するタイミングを見て焦らず進めました。焦ることなく、赤ちゃんの成長を見守りながら、サインを教えました。(男性)



家族全員でサインを統一して使用する
赤ちゃんにサインを教える際、家族全員で統一して使うことで、混乱を避けました。家族が一貫してサインを使うことで、赤ちゃんは覚えやすくなり、スムーズにコミュニケーションできました。(女性)
ベビーサインで後悔!?よくある質問
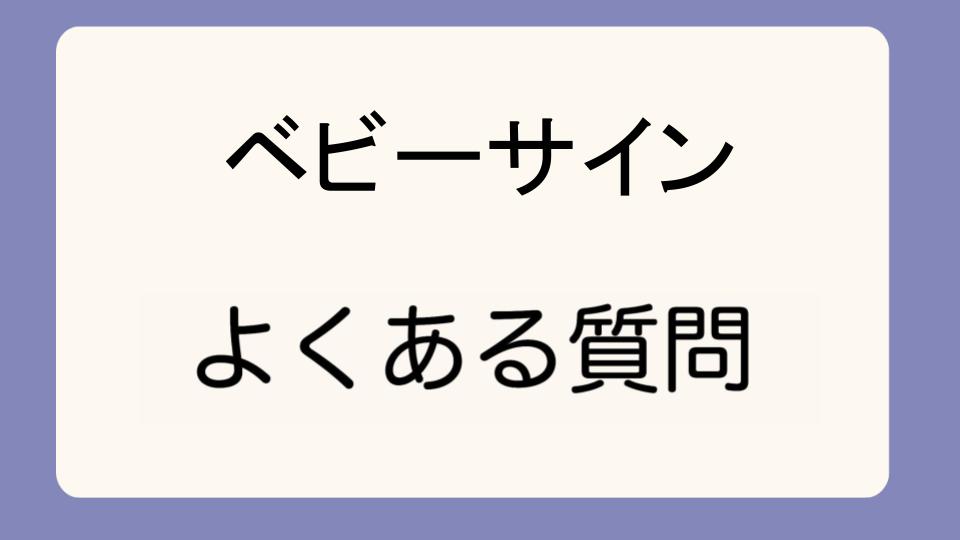
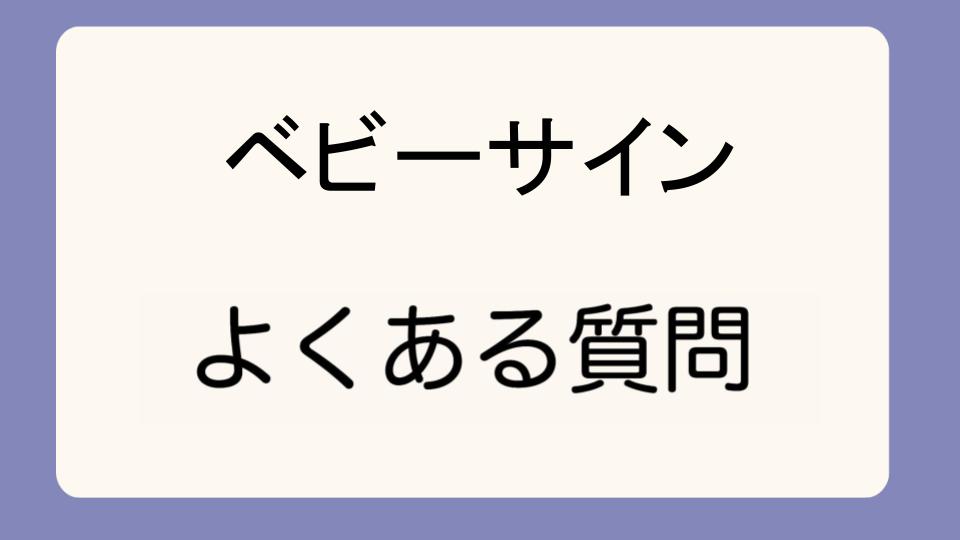
ベビーサインで後悔に関連してよくある質問をご紹介します。
ベビーサインをやめて後悔した理由とは
ベビーサインを始めたものの、途中でやめてしまったことを後悔する親も少なくありません。その理由の一つは、サインを続けなかったことで、赤ちゃんとのコミュニケーションがうまく取れなかったことです。サインを覚えたはずなのに、言葉にするタイミングを逃し、結果として赤ちゃんの意思をきちんと理解できなかったと感じました。
また、サインを学ばせることで、赤ちゃんが自分の感情を上手に伝える方法を学ぶことができたのに、それを途中で断念することで、コミュニケーションの成長の機会を逃したことも後悔の一因です。サインがあることで、親子の絆を深め、子供の言語発達を助けることができたのに、それを実現できなかったことに気づくと悔しい気持ちが湧いてきます。
加えて、サインを途中でやめると、親自身が育児の方法を見失い、他の育児方法に切り替えるのが難しくなります。特に初めての育児では、どの方法がベストかを模索する中で、サインがうまくいった場合の安心感が消えてしまい、育児に対する自信を失うことにも繋がりかねません。



途中でサインをやめると、後から「やっておけばよかった」と思うことが多いです。
ベビーサインを始めるべき時期はいつからか
ベビーサインを始める理想的な時期は、生後6ヶ月から8ヶ月の間が目安です。この時期、赤ちゃんは手や指を使って物を掴むことができ、簡単なジェスチャーを模倣する力も備わってきます。この段階でサインを始めると、赤ちゃんは自然にサインを覚えていき、日常生活の中で使えるようになります。
ただし、早すぎると赤ちゃんがサインを理解する能力が追いつかないこともあります。逆に、遅すぎても言葉を覚える段階に入ってからサインを導入すると、言葉の発達を妨げてしまう可能性も。赤ちゃんが目と耳でコミュニケーションを学べる時期を見極めることが大切です。
また、赤ちゃんの個人差を考慮することも重要です。すべての赤ちゃんが6ヶ月頃にサインを理解できるわけではないため、無理に早く始めるのではなく、赤ちゃんが反応し始めるタイミングを見守ることが大切です。親として、焦らず、赤ちゃんに合わせてサインを取り入れていきましょう。



赤ちゃんに無理なくサインを教えることが、成長を助けるカギです。
ベビーサインのやり方を間違えると危ない理由
ベビーサインを間違った方法で教えると、赤ちゃんに誤ったメッセージを伝えてしまうことがあります。例えば、サインを強制的に覚えさせようとしたり、正しいタイミングで使わなかったりすると、赤ちゃんが混乱してしまいます。その結果、サインを覚えるどころか、逆に言葉を覚えるのが遅くなってしまうリスクもあります。
また、サインを教える際に、赤ちゃんが興味を持たないサインを無理に使わせると、赤ちゃんのストレスが溜まり、サインに対して否定的な態度を取る可能性があります。興味を持つサインを選び、楽しく覚える環境を作ることが大切です。
さらに、サインだけに頼りすぎてしまうと、赤ちゃんが言葉でのコミュニケーションに遅れをとることもあります。サインと一緒に、言葉をしっかり使いながら教えることで、赤ちゃんの言語発達を促進することができ、サインがあくまで補助的な役割を果たすことになります。



サインはあくまで補助ツールであり、言葉と一緒に進めていくことが大切です。
ベビーサイン一覧で覚えるべき基本サイン
ベビーサインを学び始めたとき、最初に覚えるべき基本サインは、赤ちゃんとのコミュニケーションをスムーズにするために非常に重要です。おっぱい・ミルク、もっと、おしまい、ねんねなどは、毎日の生活で頻繁に使うサインであり、赤ちゃんもすぐに覚えやすいものです。
これらのサインは、赤ちゃんが「お腹がすいた」「もっと食べたい」「遊びが終わった」など、簡単に自分の気持ちを伝えるための手段として役立ちます。特に、食事や寝かしつけの時に使用することで、赤ちゃんとの意志疎通がより円滑になります。
さらに、赤ちゃんの興味を引くサインとして「おいしい」や「お風呂」なども追加できます。日常的に使うことで、赤ちゃんもその意味を理解しやすくなるので、覚えるスピードが早くなります。
サインを覚えることで、赤ちゃんはコミュニケーションの楽しさを学び、親との絆が深まります。最初は少しずつサインを覚えさせ、赤ちゃんが覚えたタイミングで新しいサインを追加するのがポイントです。
また、サインを教える際は、無理に押し付けず、赤ちゃんのペースに合わせることが大切です。焦らずに楽しく進めていくことで、赤ちゃんもリラックスしてサインを覚えやすくなります。
基本的なサインは、言葉が出る前のコミュニケーション手段として非常に効果的です。親と赤ちゃんが一緒に学ぶ時間を楽しむことが、育児をさらに楽しくしてくれるでしょう。



基本サインを覚えることが、赤ちゃんとのコミュニケーションを豊かにします。
ベビーサインを試してお腹いっぱいを伝える方法
赤ちゃんが「お腹がいっぱい」を伝えたがる時、ベビーサインを活用することで、親はそのサインを理解し、よりスムーズに育児を進めることができます。代表的なサインは「食べる」「もっと」「おしまい」などです。
「食べる」のサインは、赤ちゃんが食事の準備ができたことを示すサインとして使われます。赤ちゃんが口を押さえる動作をすることで、「食べる準備ができている」という気持ちを表現します。
さらに「もっと」のサインを使えば、赤ちゃんが食事を楽しんでいる時や追加で食べたいときに使います。赤ちゃんが満腹で「もう終わり」と言いたい場合には、「おしまい」のサインを見せることで、親にその意思を伝えることができます。
お腹がいっぱいになったときに「おしまい」とサインを使うことで、赤ちゃんは自分がもう満腹であることを親に伝えやすくなります。これによって無駄な食事の時間やストレスが減少します。
また、最初はサインが少し分かりにくいこともありますが、赤ちゃんがサインを使って伝えようとするその成長過程を楽しむことが育児の醍醐味です。
ベビーサインを教えると、赤ちゃんの言葉の発達を促進し、親との信頼関係を築くことができます。食事の時間がより楽しく、ストレスが少なくなります。



サインで「お腹いっぱい」を伝えることで、育児がもっと楽になります。
ベビーサインを使わず後悔しないためのポイント
ベビーサインを取り入れることを迷っている親にとって、後悔しないために知っておくべきポイントがあります。まず、赤ちゃんとのコミュニケーションを早い段階で始めることが、育児において非常に重要です。
サインを使うことで、赤ちゃんは自分の意思を伝える方法を学び、親もその意思を理解しやすくなります。これにより、泣く回数が減り、赤ちゃんとより穏やかなコミュニケーションができるようになります。
ただし、ベビーサインを強制的に覚えさせるのはNGです。赤ちゃんのペースに合わせてサインを教え、無理に進めないことが大切です。焦らず楽しんで教えることが後悔を避けるためのカギです。
また、サインを教える時期を逃さないことも重要です。赤ちゃんが手や指を使えるようになる生後6~8ヶ月がサインを始めるタイミングとして最適です。この時期を過ぎると、サインを覚えるのが難しくなることがあります。
サインを使うことで、赤ちゃんは自己表現を学び、親は育児の中で自信を持つことができます。ベビーサインを取り入れることで、赤ちゃんとの絆が深まり、より良い育児が実現します。
後悔しないためには、サインを取り入れるメリットを理解し、実践することが大切です。無理せず、楽しく育児を進めていきましょう。



ベビーサインを取り入れることで、赤ちゃんとの関係がより豊かになります。
ベビーサインをやってみたけど、うまくいかなかった場合の対処法
ベビーサインを取り入れてみたものの、思うように進まないこともあります。その場合、まず最初に確認したいのは、赤ちゃんのペースに合わせることです。無理にサインを覚えさせようとするのではなく、赤ちゃんが自然にサインを覚えられる環境を整えることが大切です。
例えば、赤ちゃんがサインを覚えないと焦ってしまうこともありますが、ベビーサインは一夜にして習得するものではありません。赤ちゃんは自分のペースで学んでいくので、親も気長に待つ姿勢が重要です。
もし、何度も試しているのにサインに反応がない場合は、サインを使うタイミングやシーンを変えてみましょう。例えば、おっぱいの時間やオムツ替えなど、赤ちゃんが日常的に触れる瞬間を利用してサインを見せると効果的です。
また、サインを見せるだけでなく、言葉でも一緒に伝えることで、赤ちゃんはサインとともにその意味を理解しやすくなります。言葉とサインを一緒に使うことで、赤ちゃんがより理解しやすくなります。
それでもうまくいかない場合は、専門的な書籍や動画を参考にして、サインの正しい方法を再確認することが有効です。サインのやり方を再チェックすることで、赤ちゃんにより効果的に伝える方法が見えてくることもあります。
最後に、赤ちゃんが反応してくれた時には、たくさん褒めてあげてください。成功体験が赤ちゃんに自信を与え、次のサインへのモチベーションを高めます。



赤ちゃんのペースで無理せずに進めることが大切です。
ベビーサイン本を参考にして学ぶ効果的な方法
ベビーサインを学ぶ際、本を活用することは非常に効果的です。専門書やガイド本を使うことで、正しいサインを覚えやすくなりますし、具体的な例が紹介されているため、実践しやすくなります。
例えば、「ベビーサインの教科書」などの書籍には、赤ちゃんにとって覚えやすいサインが段階的に紹介されており、初心者でも取り組みやすいです。サインを覚える過程が明確に示されているため、順を追って学べます。
また、ベビーサイン本には、赤ちゃんとの接し方やサインを効果的に教える方法も書かれているため、書籍を読みながら実践することができます。具体的なシーンやタイミングが解説されており、実生活に役立ちます。
さらに、DVDやオンラインで動画がついている書籍もあり、実際にサインを見ながら学べるのがポイントです。赤ちゃんと一緒に視覚的に覚えることができるため、実践的な学習が可能です。
本を参考にする場合は、赤ちゃんがサインに反応しやすい時期に合わせて学びを進めることが大切です。サインを覚えるには時間がかかることもあるため、焦らずに少しずつ覚えていきましょう。
また、サイン本は複数冊買う必要はなく、最初は1冊に絞って、しっかり学んでいくことが効果的です。選ぶ際には、実用的で具体的な内容が載っている本を選ぶと良いでしょう。



本を活用することで、サインを効率よく学ぶことができます。
ベビーサインで危ないと感じた瞬間の対策
ベビーサインを学んでいると、赤ちゃんの反応や行動に危険を感じる瞬間があるかもしれません。そんな時、冷静に対処することが最も大切です。赤ちゃんがサインを使うことで、日常のコミュニケーションが円滑になりますが、サインのやり方に注意が必要です。
例えば、「痛い」というサインを使うことで、赤ちゃんが何かを感じ取っている場合があります。もし赤ちゃんが痛がっているようなサインを出した場合、その背後に何か問題がないか確認しましょう。体調や安全面に問題がないか、早急にチェックすることが重要です。
また、赤ちゃんが「危ない」と感じる行動をサインで表すことがあります。例えば、赤ちゃんが高いところに手を伸ばしたり、危険なものに近づいた時、親がそのサインを見逃さないようにすることが大切です。
サインだけでなく、言葉での指示も加えると、赤ちゃんが理解しやすくなります。「これ、危ないよ」「こっちに来てね」といった言葉を合わせて伝えることで、赤ちゃんが自分の行動を調整しやすくなります。
さらに、サインを使って安全に関する指導を行うことも可能です。例えば、「危ない」と「痛い」というサインを理解させることで、赤ちゃんが自己保護する能力が育ちます。
サインを通じて赤ちゃんと安全に関する意識を高めることができる一方、危険を感じたらすぐに対策を講じることが最も大切です。常に赤ちゃんの状態を確認し、適切な対応をするように心がけましょう。



危険を感じた時には、冷静に状況を確認して対処しましょう。
まとめ|ベビーサインで後悔しないために知っておくべきポイントとは
最後にこの記事のポイントをまとめてご紹介します。
- ベビーサインは赤ちゃんのコミュニケーション手段として役立つ
- サインを教えるタイミングや方法に個人差がある
- 焦らず赤ちゃんのペースで進めることが大切
- サインを使うタイミングを生活の中に自然に取り入れる
- サインと一緒に言葉を使うと理解が深まりやすい
- 赤ちゃんがサインに反応しなくても焦らず待つ
- 無理にサインを覚えさせようとしないことが重要
- サインを使ってコミュニケーションが取れるようになると親子の絆が深まる
- 本や動画を参考にして正しいサインを学ぶと効果的
- ベビーサインを使わずに後悔しないためには焦らず試すことが重要
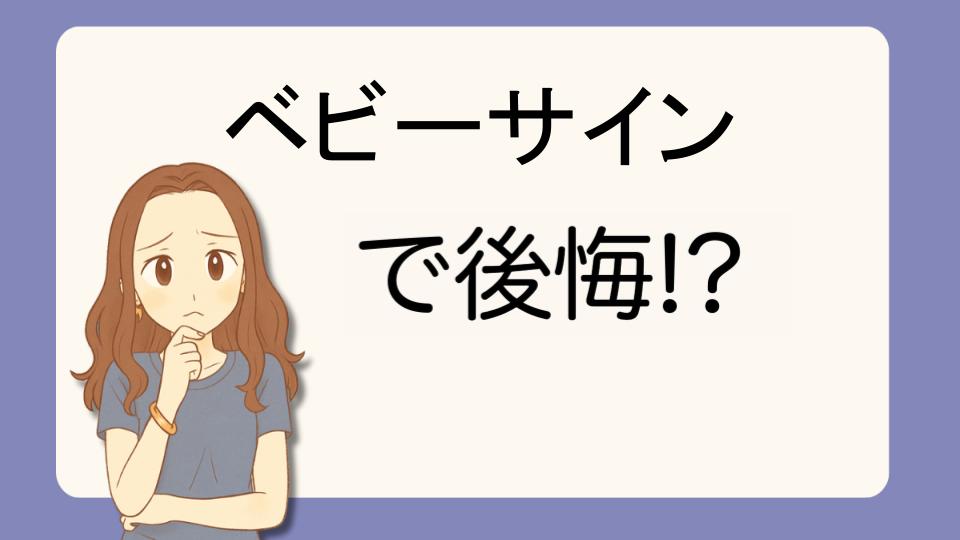
コメント